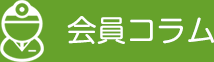会員コラム:植物と虫と人間と さわ小児科クリニック 澤 大介
今年、庭先で見慣れない虫が目につくようになりました。キオビエダシャクという蛾の一種で、イヌマキ(ヒトツバ)を好んで食害するそうです。我が家にはイヌマキを植えていないため、幸いなことに直接の被害は出ていません。
とはいえ、小さな花壇や鉢植えにはさまざまな植物が育ち、それを目当てに多くの虫や鳥がやって来ます。愛らしい虫もいれば、一般的に「害虫」と呼ばれるような存在も少なくありません。日々の庭仕事のなかで、そんな虫たちとの付き合い方を考えることが増えました。
たとえば、夏場によく見かけるコガネムシ。幼いころから見慣れている虫ですが、花壇を掘ると必ずといってよいほど幼虫がいて、植物の根を食べてしまいます。以前はあまり気に留めていませんでしたが、最近は被害が大きく、土に薬剤を混ぜ込んで幼虫対策をしています。一方、成虫については、蝶やトンボ、カナブンと同じように子どものころから親しんできた存在なので、駆除するのは心苦しく感じてしまいます。そのため、ブルーベリーの近くにはミント等を植え、近づかないでもらう工夫をしています。花壇に関しては、年に2回の植え替え時に幼虫が見つかったときだけ、やむを得ず退場してもらうようにしています。
カメムシもよく見かけます。春はそら豆、夏はトマトに集まることが多く、大量発生というほどではありませんが、見つけたときは割り箸でつまんで遠くに移動してもらっています。益虫といわれる種類もいるようですが、目にするのはたいてい害虫とされるカメムシなので、できるだけ距離を置くようにしています。
そら豆にはアブラムシもやってきます。発育不良や病気の原因になることもありますが、殺虫剤はできるだけ使わず、お酢のスプレーやガムテープなどで対応しています。その理由のひとつに、アブラムシの天敵であるテントウムシの姿を観察するのが楽しみだからということがあります。ときどき見かけるテントウムシに似た「テントウムシダマシ」は、割り箸でそっとどこかに移動してもらっています。
プランターの下にはダンゴムシもよく潜んでいます。基本的には悪さはしませんが、新芽を食べてしまうことがあるので、種まきの時期は注意が必要です。ポットを使って発芽させたり、花壇に直接種をまく場合は、木酢液を撒いてダンゴムシを遠ざけるようにしています。
庭の植物に致命的な被害が出ないかぎり、虫たちを積極的に駆除することはあまりありません。今回大量発生したキオビエダシャクについても、我が家では被害がなかったためそのままにしていましたが、ご近所にはイヌマキを生け垣にしているお宅もあり、今になって考えると少し申し訳ない気持ちになります。次に見つけたときには、駆除という選択肢も取るつもりです。
植物と虫と人間と。決して仲良しではないけれど、どこかでバランスをとりながら、一緒に季節を過ごしていけたら。そんなふうに思いながら、植物と虫との暮らしを楽しんでいます。